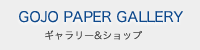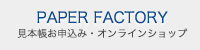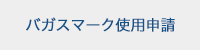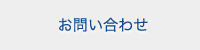紙の豆知識 <紙の歴史>
紙のない時代

紙の誕生前、絵や文字の記録材料には様々なものを使っていました。亀の甲、石、粘土板、ヤシの葉、羊の皮、木簡、絹などがありましたが、その中でも一番紙に似たものがパピルスです。パピルスは紀元前3000年頃、エジプトにて用いられるようになりました。
パピルスとはパピルス草の茎を細かく裂いて縦横に並べ、シート状にしたものです。パピルスは英語の「paper」を始めとして、ヨーロッパ諸国の「紙」の語源になっています。
しかし、パピルスは書写材料であっても「紙」ではありません。紙とは「植物繊維であるパルプやその他の繊維を水中で叩き、ばらばらにほぐして、漉き上げて薄く平らに伸ばしたもの」と定義されます。つまり、紙とは繊維を強く絡み合わせて作られているものですので、パピルスは「漉く」という工程がないため、紙とはいえないのです。
紙の発明
現在の紙と呼ばれているものの製法は西暦105年、中国の蔡倫によって確立されたといわれています。これは「蔡侯紙(さいこうし)」と呼ばれ、書写材料としての機能を持つ最古のものとなります。当時の原料は樹皮、ぼろ布、麻繊維、魚網であったと伝えられていますので、現在の紙のルーツは今でいう「非木材紙」であったといえます。
以前、蔡侯紙が作られる200年以上前の前漢時代に作られた「はきょう紙」が最古の紙という説が浮上していましたが、現在でははきょう紙は繊維であって紙ではないという結論に達したようです。はきょう紙は書写材料としてではなく、貴重品などを包む包装紙として使われていたと考えられています。
日本の紙

日本の製紙技術は610年に朝鮮半島高句麗の僧、曇徴により伝えられたとされていますが、実際にはもっと早くから伝えられていたのではないかとの説もあります。
日本の紙の原料は麻ではなく楮(こうぞ)であったため、日本独自の「和紙」を生み出すことができたのです。日本最古の紙は702年に製造されたもので、現在は奈良県の正倉院に保管されています。紙が伝わった当初は写経材料として使われていたため、日本の紙はより完成度が高まっていったと考えられています。
日本の「紙」が「カミ」と発音され始めたのは奈良時代です。その語源は、紙以前の書写材料であった木簡の簡(かん、かぬ)が変化したものといわれていま す。他にも原料としていた楮の樹皮の「皮」から音韻が変化したものとの説などいくつかありますが、本当のところはよくわかっていません。